「ふるさと納税はお得なのでぜひやってみましょう!」とよくメディアなどで紹介されていますよね。
確かにふるさと納税はお得な制度ですが、ふるさと納税にはいくつかデメリットもあります。
今回は【知っていると得する】ふるさと納税をする際のデメリットの対策、解決策を紹介というテーマでふるさと納税のデメリットへの対策、解決策を紹介します。
ふるさと納税のデメリットについては、以前の記事で紹介しましたので参考にしてください。
ふるさと納税についてまだよく知らないという方は、初心者の方にもわかりやすく説明した記事もありますので、こちらを参考にしてみてください。
ふるさと納税という制度を、いかにお得に利用するかは,まずはその制度について知ることが重要です。
それではふるさと納税デメリットへの対策、解決策を紹介していきます。
ふるさと納税の限度額を超えないためには?

ふるさと納税には控除限度額があります。
寄付した額から2,000円を引いた額が所得税や住民税の控除対象として戻ってきますが、その寄付額の上限つまり控除限度額は年収や扶養家族、住宅ローンの有無によって変わります。
その控除限度額の上限を超えて寄付をする事はできるのですが、上限以上の寄付金は全て自己負担となります。
そこで「控除限度額の上限を超えないようにするにはどうすればいいの?」という疑問が出てくると思います。
その対策・解決策は事前に限度額をシミュレーションしておくことです。
計算式はあるのですが、計算するのが面倒な場合は、インターネットサイトで簡単に計算できるものがありますので、だいたいの控除限度額を知りたい場合にはこちらがおすすめです。
楽天ふるさと納税簡単シミュレーターはこちら
シミュレーションする事で、自分の控除限度額を把握できます。
上限を超えないように調整し、ふるさと納税のメリットを最大限に活用できるといいですね。
寄付する自治体の数によって申請方法に違いがある
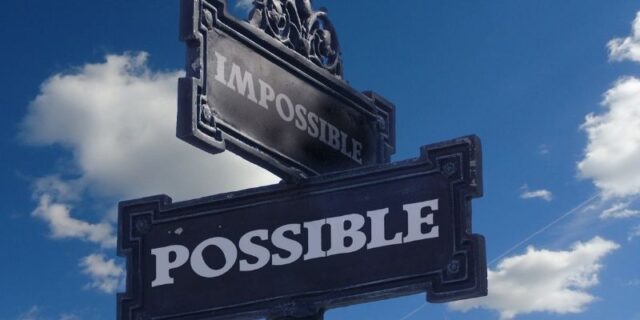
確定申告なしで、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度に「ワンストップ特例制度」があります。
このワンストップ特例制度は給与所得が2,000万円以内の会社員で、1年間の寄付先が5自治体以内の場合に活用できるというものです。
申請の方法は簡単で、ワンストップ特例制度の申請用紙、本人の確認書類(運転免許証など)の写しを納付先の自治体に送るだけです。
この制度での控除は住民税のみになりますが、本来所得税から還付されるはずの金額分が住民税から控除されるので総額は確定申告の時と変わりません。
また寄付先が6自治体以上になると確定申告での申請となります。
確定申告というと、面倒で難しいイメージがありますが、ふるさと納税の確定申告はそこまで難しくありません。
寄付する自治体の数によって申請方法が違うことの対策としては、寄付する自治体が5自治体以内なら、ワンストップ特例制度で申請できるので、確定申告しなくてもふるさと納税ができると知っておくことが必要です。
知識を身につけてから行うのがおすすめ

いかがでしたか?
今回は【知って得する】ふるさと納税をする際のデメリットの対策・解決策を紹介というテーマでお伝えしました。
ふるさと納税はお得な制度ですが、メリットだけでなくデメリットもあります。
しかしそのデメリットを知り、さらにその対策・解決策を知っておけば、ふるさと納税のメリットを最大限に受けられます。
今回紹介したふるさと納税のデメリットの対策・解決策は以下の通りです。
- 事前に限度額をシミュレーションしておく
- 寄付する自治体の数によって申請方法が異なると知っておく
ふるさと納税の仕組みや、メリット、デメリットについて知り、さらにデメリットの対策・解決策まで知っておけば、この制度のメリットを最大限に活用できると思います。
せっかくのお得な制度なので、しっかり理解した上で行うのがおすすめです。
以上、参考になればうれしいです。
最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。
それでは今日も、よい1日を!





コメント